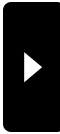2018年06月25日
初使い
我が家の台所は業務用に使えるようになっています。家を建て替えた時に、将来自宅で飲食店ができるようにと設計したのです。
なので広くて使いやすいし、ガス台も業務用なので火力が強くて調理も早い。が、ひとつだけ今まで私が使いこなせなかったものがあります。それは「ガスオーブン」
ガス台と一体式でとても大型。パンを焼いたら一気に4斤は焼けてしまうぐらいの天板の大きさです。なのに。。。今まで一回も使わずに14年間。
何となく使い勝手がわからない、使ったら汚れて掃除が面倒臭そう、オーブン料理はお客様用、みたいな固定観念があって、オーブンには手を出せずにいたのです。
しか~し!
今回はどうしてもオーブンを使わなくてはいけない事態となり。。。(理由は約1年後に判明しますが、今は秘密( ;∀;))
重い腰を上げて、「禁断のガスオーブン」を使ってみました!
結果は、「何でもっと早く使わなかったのかなぁ!あ~、もったいない、こんなに便利なものを使わずにいたなんて!!」
そんなものですよねぇ、食わず嫌いのようなもの(-_-;)
「おやき」は信州のスローフードです。
「ふきっ子おやき」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
2016年07月24日
ビニール袋
ビニール袋って、とっても重宝ですよね。保存はもちろん調理にも大活躍してくれて、台所の必需品です。
このビニール袋で簡単な真空パックをしてしまうのが、最近のわたしのハマりごと。
肉や野菜に味付けをする時に、ビニール袋に食材と調味液を入れて口をしっかり縛りますよね。その時にひと手間掛けると、少ない調味液でしっかり味が浸み込むんです。
水を張った大きめのボールを用意して、食材と調味液を入れたビニール袋を水の中に入れます。
水の中で、ビニール袋の中の空気を抜くように口を押えながら絞っていきます。最後に調味液が溢れるか溢れないか、ぐらいまできたら、水の中でビニール袋の口を縛ります。
これで簡単真空パックの出来上がり!意外と重宝ですよ!
きょうからお出しする百十そばの前菜「夏野菜のピクルス」も、少ないピクルス液でこの通り!(^^)!
「おやき」は信州のスローフードです。
「ふきっ子おやき」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
2014年10月20日
唐箕
この週末は何とも目まぐるしい2日間でした。
土曜日は蕎麦の唐箕(とうみ)掛け、日曜日は紅玉のジャム作り。どちらも興味があって、店はお願いしておやきを作ってすぐに飛び出す2日間でした。
蕎麦は収穫した時点では他の種子や雑草、茎、昆虫などが入り混じっています。それを唐箕にかけて選別するのです。
昔はお米も唐箕をかけて選別しましたが、今はコンバインでその作業もすべてやってくれるので、唐箕が家にある農家も少なくなったようですが。
わたしも唐箕を見ること自体が初めてで興味津々。

この写真を撮る前に、吹き出し口の真ん前に立ってしまって、全身にゴミくずが降りかかってしまいました

「そんなとこに立ってるからさ」って、もっと早く言ってくださいよ


唐箕をかけたものの、イマイチ乾燥が足りないようなので分けて乾燥しようということになって、私の割り当て60キロを担いできたわけです。
きょう一日乾燥できればOKだったのですが、どうやら午後から雨のようでお昼には袋入れに戻ってこなくてはならないようです。
蕎麦の種蒔きから収穫、乾燥まで、一通りの作業をお手伝いして、なおさら蕎麦の実が愛おしい気持ちになりました。
いよいよ今度は新蕎麦の蕎麦打ちです

っと、その前に原稿を書き終えなくちゃ


「おやき」は「信州のスローフードです。
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
2014年05月30日
包丁研ぎ
お店の包丁は全部で7本。その包丁を研ぐのはわたしの役目。
きのうも「野菜の力」をお話ししましたが、野菜は旅モノより地モノ、それも露地モノが一番おいしいと思いますが、同時にアクも凄い。
これから収穫を迎える丸なすは20個も整形していると包丁はアクが付いて切れなくなってきます。
だから、包丁研ぎは頻繁に行わないとイケナイ、、、のですが、これが7本も一気に研ぐとなると時間と気力が必要で
結果、週1回研げればいい方なのです(お寿司屋さんだったら毎日ですよね )
)
でも、研いだ翌日にスタッフから「ヨウコさん、包丁よ~く切れますね!」って言われるとうれしくなってしまいます。
なぜ、こんな話をしているかというと、そろそろお店の包丁が切れなくなってきていて、きょうあたり研がなくちゃ、って思いながら気合が入らない朝を迎えているので、自分に喝っ!って思ってブログアップしたわけ

さあ、きょうはセッセと包丁研ぎまっせ

(先日油揚げを切っていたら、あまりにも見事に並んでいるので思わず写真を撮ってしまいました )
)
「おやき」は「信州のスローフードです。
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
きのうも「野菜の力」をお話ししましたが、野菜は旅モノより地モノ、それも露地モノが一番おいしいと思いますが、同時にアクも凄い。
これから収穫を迎える丸なすは20個も整形していると包丁はアクが付いて切れなくなってきます。
だから、包丁研ぎは頻繁に行わないとイケナイ、、、のですが、これが7本も一気に研ぐとなると時間と気力が必要で

結果、週1回研げればいい方なのです(お寿司屋さんだったら毎日ですよね
 )
)でも、研いだ翌日にスタッフから「ヨウコさん、包丁よ~く切れますね!」って言われるとうれしくなってしまいます。
なぜ、こんな話をしているかというと、そろそろお店の包丁が切れなくなってきていて、きょうあたり研がなくちゃ、って思いながら気合が入らない朝を迎えているので、自分に喝っ!って思ってブログアップしたわけ


さあ、きょうはセッセと包丁研ぎまっせ


(先日油揚げを切っていたら、あまりにも見事に並んでいるので思わず写真を撮ってしまいました
 )
)「おやき」は「信州のスローフードです。
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
2012年03月31日
過保護なボイラー
まさしく「過保護なボイラー」です。

この冬、厨房の中で一番手厚く扱われたのはこのボイラーです。
なぜかというと、氷点下の寒さの中で水を入れ、ガスを捻って火をつけると、しばらくして止まってしまう。
朝の一番忙しい時間帯に突然止まってしまったことが2度3度。
メーカーさんに来ていただいても、原因がわからず。。。
でも、どうやら原因は水滴だったようで、冷たい水を入れてすぐに火をつけると、タンクの表面に水滴が付き始め、それが種火に滴り落ちて火を消していたみたいなのです。
原因がわかったので、それ以降は朝一番でまずお湯をたっぷりと入れて、前面ガードを外してストーブで全体を温めて、それから点火。
この冬は人間様より、ボイラー様に温まっていただきました
そんな過保護も春本番になって、そろそろ終わりの時期を迎えたようです。
おやき屋にとっては「命」のボイラー。これからは何事もなく稼働してくれることを願うばかりです。
「おやき」は信州のスローフードです。
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
この冬、厨房の中で一番手厚く扱われたのはこのボイラーです。
なぜかというと、氷点下の寒さの中で水を入れ、ガスを捻って火をつけると、しばらくして止まってしまう。
朝の一番忙しい時間帯に突然止まってしまったことが2度3度。
メーカーさんに来ていただいても、原因がわからず。。。
でも、どうやら原因は水滴だったようで、冷たい水を入れてすぐに火をつけると、タンクの表面に水滴が付き始め、それが種火に滴り落ちて火を消していたみたいなのです。
原因がわかったので、それ以降は朝一番でまずお湯をたっぷりと入れて、前面ガードを外してストーブで全体を温めて、それから点火。
この冬は人間様より、ボイラー様に温まっていただきました

そんな過保護も春本番になって、そろそろ終わりの時期を迎えたようです。
おやき屋にとっては「命」のボイラー。これからは何事もなく稼働してくれることを願うばかりです。
「おやき」は信州のスローフードです。
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
2011年12月15日
削り器
先日、お師匠さんのお宅にお邪魔した際に見つけたもの。
これ、今や滅多にお目にかからないですよね。
鰹節の削り器です。
でも、これは普通の削り器ではないんです。
蓋の裏側にストッパーとなる刃がついていて、鰹節が小さくなっても安全に削ることができる優れもの。
その名も、
「にんべん式安全削器」とあります。
昔、お師匠さんの娘さんがにんべんに勤めていた頃に、この安全削器が製造されて、社員全員が一器づついただいたのだそうです。
今、にんべんのHPを見ても、安全削器は販売されていないので、これは貴重品かも

でも、削り器を見ているだけで心が落ち着くし、昔懐かしくなります。
ゆっくりと鰹節を削って、料理をする。
こんなユッタリズムの生活を取り戻せたら、とつくづく思うのでした。
「おやき」は信州のスローフードです。
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
2009年03月03日
エコバック
きのう従姉が送ってきた写真。
今、話題の新聞から作るエコバックです。
考案者は高知県の主婦ですが、NHKニュースで放送されてから一躍全国版で普及し始めたようです。
わたしもこのニュースを見ていて、確かに頑丈そうで
『ショッピングバックにいいかも・・・』
って思っていましたが、既に長野でも作られ始めていたんですね。
従姉の作っているこのタイプは小型版で、ちょっとした小物入れ用にも使えそうです。わたしも作り方教わろうっと。。って、いつ作るんだい?という話もありますが

今朝、改めてネット検索してみたら、レシピをネット販売しておりました。
物を売るのではなく、ノウハウを売る
何だか目からウロコ

距離を縮める、可能性を広げる。まさしくエコビジネスですね。
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
2009年02月24日
お雛さま
おやきフェアから一夜明けて、きのうはお昼も夜も外食でした。
お昼は善光寺山門の「藤屋御本陣」で優雅にランチ。
ここ、一度来てみたかったんです~
フェアのお手伝いに来てくれた横浜の妹曰く「長野にいるのか、東京にいるのか、わからない」というほど、洗練されているイタリア料理店。お値段も1,000円からあるし、パスタも4種から選べるし、デザートも単品で400円と、高級感漂う雰囲気からすればリーズナブルな価格で、おススメのお店でした。。。写真は撮り忘れた
夜は商工会支部総会でご近所の「悠善」へ
昼間のイタリアンもいいけれど、ここ悠善へ来てやっぱり日本料理はいいなあと思ってしまいました。
これが前菜の盛り合わせ。


お雛さまの器なんて、世界中探しても日本にしかないですよね、きっと
食材からも、器からも、盛り付けからも四季を感じられる日本料理って、やっぱり奥が深いです。
こちらも→おやき屋店主の日掛け帳ー番外編 http://blog.livedoor.jp/fukikko2/
お昼は善光寺山門の「藤屋御本陣」で優雅にランチ。
ここ、一度来てみたかったんです~

フェアのお手伝いに来てくれた横浜の妹曰く「長野にいるのか、東京にいるのか、わからない」というほど、洗練されているイタリア料理店。お値段も1,000円からあるし、パスタも4種から選べるし、デザートも単品で400円と、高級感漂う雰囲気からすればリーズナブルな価格で、おススメのお店でした。。。写真は撮り忘れた

夜は商工会支部総会でご近所の「悠善」へ
昼間のイタリアンもいいけれど、ここ悠善へ来てやっぱり日本料理はいいなあと思ってしまいました。
これが前菜の盛り合わせ。
お雛さまの器なんて、世界中探しても日本にしかないですよね、きっと

食材からも、器からも、盛り付けからも四季を感じられる日本料理って、やっぱり奥が深いです。
こちらも→おやき屋店主の日掛け帳ー番外編 http://blog.livedoor.jp/fukikko2/
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
2008年12月09日
センゾツキ
今も厨房で使っているのが、この「せんつき」です。

今や「万能カッター」なるものが手軽に買える時代ですが、ふきっ子のお八起ではこの「せんつき」が欠かせません。
手切りにこだわっているのに、「せんつき」使うの?って言われそうですが、この「せんつき」を使う理由もやはりこだわりがあるんです。
万能カッターや包丁を使うと、繊維がスパッと切れてしまいます。でも、このせんつきで野菜を突くと繊維を壊しながら切れていきます。この不揃いな野菜の断面から味が沁みこんでいくので、味が早く回り、ノッペリとした味付けになりません。
こう実感できたのは、実はつい最近のこと
もちろんわたしもぴあんさんと同様?にせん切りはキライ!それに、この「せんつき」も手を突きそう(過去何回も突いてますが )で最初は恐かった~。
)で最初は恐かった~。
でも今では「せんつき」の魅力に開眼してしまいました。
特にこの野沢菜かぶに「せんつき」は欠かせません。

野沢菜の原種と言われる「天王寺かぶ」。古くは野沢菜も大きなかぶが出来ることが特徴だったのですが、いつのまにかお菜が主流になって、かぶを食すことも少なくなってきてしまいました。
昔は、万能カッターもない時代にこのかぶをせん切りにするには「せんつき」が必需品でした。金子萬平さん著の「おやき・焼餅の話」によると、この「せんつき」は「センゾツキ」と呼ばれていたそうです。「センゾ」とは細かく刻むこと、大根を千六本に切ったもの、などの意味。
厨房で何気なく使っている道具たちにも歴史があり、それを知ることで愛着が生まれます。
「せんつき」これからも大切に使わせていただきます
こちらも→おやき屋店主の日掛け帳ー番外編 http://blog.livedoor.jp/fukikko2/
今や「万能カッター」なるものが手軽に買える時代ですが、ふきっ子のお八起ではこの「せんつき」が欠かせません。
手切りにこだわっているのに、「せんつき」使うの?って言われそうですが、この「せんつき」を使う理由もやはりこだわりがあるんです。
万能カッターや包丁を使うと、繊維がスパッと切れてしまいます。でも、このせんつきで野菜を突くと繊維を壊しながら切れていきます。この不揃いな野菜の断面から味が沁みこんでいくので、味が早く回り、ノッペリとした味付けになりません。
こう実感できたのは、実はつい最近のこと

もちろんわたしもぴあんさんと同様?にせん切りはキライ!それに、この「せんつき」も手を突きそう(過去何回も突いてますが
 )で最初は恐かった~。
)で最初は恐かった~。でも今では「せんつき」の魅力に開眼してしまいました。
特にこの野沢菜かぶに「せんつき」は欠かせません。
野沢菜の原種と言われる「天王寺かぶ」。古くは野沢菜も大きなかぶが出来ることが特徴だったのですが、いつのまにかお菜が主流になって、かぶを食すことも少なくなってきてしまいました。
昔は、万能カッターもない時代にこのかぶをせん切りにするには「せんつき」が必需品でした。金子萬平さん著の「おやき・焼餅の話」によると、この「せんつき」は「センゾツキ」と呼ばれていたそうです。「センゾ」とは細かく刻むこと、大根を千六本に切ったもの、などの意味。
厨房で何気なく使っている道具たちにも歴史があり、それを知ることで愛着が生まれます。
「せんつき」これからも大切に使わせていただきます

こちらも→おやき屋店主の日掛け帳ー番外編 http://blog.livedoor.jp/fukikko2/
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
2008年06月03日
子供服?
どう見ても、これって子供服?
でも、これ「お手拭タオル」なんです。
こんな風にハンガーにかけて使います。
母が知り合いからいただいてきた時、タンスの前に掛けてあったのでてっきり赤ちゃんの洋服が掛かっているのかと思って、母に「どうしたの?誰か赤ちゃんでもできたの?」って聞いちゃいました。
このお手拭タオルも先日の母の折り紙同様、老人センターで教えてくださる手習いのひとつだそうです。
でも、もったいなくてわが家では未だに飾ったままで~す

こちらも→おやき屋店主の日掛け帳ー番外編 http://blog.livedoor.jp/fukikko2/
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/