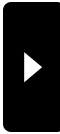2020年12月14日
試作三昧
きのうは久々に終日自宅に籠っていました。というのも週末に動画撮影をするので、その試作をしなくてはいけなくて朝から悪戦苦闘( 一一)
お題は「蕎麦粉」。家庭で簡単にできる蕎麦打ち、蕎麦粉を使った粉もん料理2種。
ということで、まな板と包丁で打つ「二八そば」に取り掛かり。。。これはまあ回数重ねれば家庭包丁での切り方も上手になるな、ぐらいで終了。
お次は「そばがき」。これこそ色々な作り方があるので、3回ほどいろいろ試作。出来立てを食べないと美味しくないので、出来上がるたびに母を呼んできて試食。
最後は「そばうすやき」。蕎麦米も使うことが条件に入っているので、ここで蕎麦米登場。蕎麦粉の薄め方がポイントで、フライパンで上手に伸ばせるぐらいの緩さにして、蕎麦米をトッピング。これは母が大絶賛。「毎日食べてもいいぐらい!」とお褒めの言葉をいただきました。
かくして昼食はそば三昧( 一一) 母とふたりで夕食が要らないほど満腹になった試作三昧の一日でした。



「おやき」は信州のスローフードです。
「ふきっ子おやき」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
2020年04月04日
「にらせんべい」作りましょう!
外出自粛が出ているこの週末。おうちで「にらせんべい」作りませんか?
長野の郷土食でありながら、どこでも手に入る安価な材料で作れちゃいます。お子さんと一緒に焼きながら、アツアツを頬張ると幸せ~な気持ちになりますよ! ポイントは焼き立てを食べること。一枚食べ終わりそうな時にまた焼くと何枚でも食べられちゃいます。薄~くカリカリに焼いてください!(^^)!
ニラせんべい(薄焼きタイプ)
材料:3枚分(26cmフライパン)
中力粉 200g
ニラ 1把(100g)
卵 (なくても可) 1個
味噌 30g
水 卵と合わせて300cc
鰹節や干しエビ(お好みで)
<作り方>
①ニラは根元を細かく、葉は1.5cmほどに切り、ボールに入れた地粉と混ぜておく。
②計量カップに卵を割り入れほぐし、水を足して300cc分計量する。
③ボウルに味噌と②の水を加えたところへ、①を入れてよく混ぜ合わせる。
④フライパンにサラダ油(分量外)を多めに引き、弱火にかける。
⑤③の生地を玉じゃくしで2杯程度フライパンに入れ、お玉の底で薄く広げる。
⑥フタをして中火で片面3分程度、フタを外して裏面3分程度焼く。
⑦好みでさらに焼き上げてもよい。
*<タレ> 好みでタレを添える。
1.砂糖醤油 (醤油 大匙1、砂糖 大匙1~2)
2.酢醤油 (醤油 大匙1/2、酢 大匙1/2、ラー油 小匙1/2、すりごま少々)

長野の郷土食でありながら、どこでも手に入る安価な材料で作れちゃいます。お子さんと一緒に焼きながら、アツアツを頬張ると幸せ~な気持ちになりますよ! ポイントは焼き立てを食べること。一枚食べ終わりそうな時にまた焼くと何枚でも食べられちゃいます。薄~くカリカリに焼いてください!(^^)!
ニラせんべい(薄焼きタイプ)
材料:3枚分(26cmフライパン)
中力粉 200g
ニラ 1把(100g)
卵 (なくても可) 1個
味噌 30g
水 卵と合わせて300cc
鰹節や干しエビ(お好みで)
<作り方>
①ニラは根元を細かく、葉は1.5cmほどに切り、ボールに入れた地粉と混ぜておく。
②計量カップに卵を割り入れほぐし、水を足して300cc分計量する。
③ボウルに味噌と②の水を加えたところへ、①を入れてよく混ぜ合わせる。
④フライパンにサラダ油(分量外)を多めに引き、弱火にかける。
⑤③の生地を玉じゃくしで2杯程度フライパンに入れ、お玉の底で薄く広げる。
⑥フタをして中火で片面3分程度、フタを外して裏面3分程度焼く。
⑦好みでさらに焼き上げてもよい。
*<タレ> 好みでタレを添える。
1.砂糖醤油 (醤油 大匙1、砂糖 大匙1~2)
2.酢醤油 (醤油 大匙1/2、酢 大匙1/2、ラー油 小匙1/2、すりごま少々)

2016年02月27日
やしょうま教室
きのうは地域の老人福祉センターで「やしょうま教室」を開催しました。
熱源がカセットコンロしかないので3割の粉は教室で、7割の粉は自宅で米粉を練ってセイロに入れて、火入れは母に頼むことにしました。こうすることで、粉を蒸す20分が短縮されるので、教室自体もスムーズに進みます。今回は開催場所と自宅が近かったので、200%地の利を活かしました!(^^)!
今回の定員は16名でしたが、センターの方によると倍以上の応募があったそうです。「やしょうま作り」はとても大変ですが、それを学びたい、作りたいという人がまだまだたくさんいることを知って、とてもうれしく思いました。
このわたしも10年ほど前に、食生活改善推進委員の講習で「やしょうま」を習ったお蔭で、こうやって教室で教えることができるまでになりました。今回の教室でも「公民館活動でやしょうまを教えたいので・・」と仰って参加されている方もいらっしゃいました。
こうやって郷土食を繋げていく輪が少しづつ広がってくれればいいなあと、きのうはつくづく感じました。
あっ、肝心のやしょうまの写真を撮り忘れたので、以前の教室の写真をアップしておきます。。。今回は市民新聞さんの取材があったので、来週の新聞に掲載されると思います。
「おやき」は信州のスローフードです。
「ふきっ子おやき」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
2015年02月09日
やしょうま
毎月おやきを作っている「おやき教室」ですが、今月は「やしょうま教室」になって、きのう来られた生徒さんの中には戸惑う人もチラホラ。
やしょうまはどちらかというと工作の部類ですから、苦手な人もいるのは当たり前ですね。でも、やっぱりこれも郷土食ですから、基本は押さえておかなくては。
ということで、初めての今年は簡単な工作やしょうまにトライ。そして出来上がったのがこちらです↓


写真の他に昔ながらの豆を入れた松模様のやしょうまも作って、やしょうま三昧な教室。
地元の方には「やしょうま」で通じますが、やしょうまをご存じない方のために。。。
「やしょうま」は米の粉を湯で練ってから蒸し、それをちぎってゆで大豆・青海苔・ごま・切刻んだ野菜等と色粉を混ぜて形を整えたものです。
2月15日(もしくは3月15日)は釈迦が入寂した日、涅槃会で、この日にお供えするのが「やしょうま」です。
名前の由来は、釈迦が入滅のときこれを食べ、傍らにいた弟子の邪(やしょ)に、「邪(やしょ)うまかったぞ」と言ったからというのが一般的ですが、もうひとつの説は、米の粉をこねて片手で握った形が馬の背に似ているので「痩せ馬」からなまったという説もあります。
「おやき」は信州のスローフードです。
「ふきっ子おやき」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
2013年07月15日
上手に出来た
きのうも暑い日でしたが、教室の生徒さんたちは暑さに耐えてこんなにたくさんのおやきを作り上げました。

写真のおやき x 2倍量のおやきです。
暑い時は、笹の葉やみょうがの葉がとても涼しげに見えます。
「おやき」は信州のスローフードです。
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
2012年02月09日
やしょうま作りました
昨日の定休日、やしょうま教室を無事に開催しました。
前日の告知にも関わらず、11名もの参加があって本当によかったです。参加いただいた皆様、ありがとうございました!
お蔭様で、段取り確認もできましたし、11日の教室に向けて若干の軌道修正もできました。
生徒さんが撮ってくれた写真とわたしの写真、少しですがアップいたします。
まずは完成品。右手前は昔ながらの松模様の黒豆やしょうま。パンダと梅もそれぞれ2種類作りました。

パンダの顔を作ってます。

梅の花びら。
普通はしばらく時間を置いてから切るのですが、教室ではまだ軟らかい状態なので糸で切っていきます。
この瞬間が一番楽しいけど、呼吸が止まる瞬間なんです

皆さん、お疲れ様でした~!

「おやき」は信州のスローフードです。
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
2012年02月07日
やしょうま作ります
突然ですが、明日の定休日に「やしょうま教室」を開催いたします。
というのは、今週土曜日に障害のある方々と一緒に「やしょうま作り」をすることになっているのですが『段取りを確認しながら一回は作っておかないと』と、思っていながら平日は全く時間が取れず。
いよいよ定休日にひとりで作ってみるしかないと思っていたのですが、どうせ作るなら、教わりたい人や見てみたい人にも声をかけちゃおう!と思ったわけです。
明日10時から本店2階の厨房で作ります。希望される方は、本日中にお店にお電話くださいませ。
電話: 026-284-2934 小出まで
作るのは「梅」「パンダ」「黒豆」の3種です。
参加費用は材料費のみ。
所要時間は2時間ほどです。


「おやき」は信州のスローフードです。
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
というのは、今週土曜日に障害のある方々と一緒に「やしょうま作り」をすることになっているのですが『段取りを確認しながら一回は作っておかないと』と、思っていながら平日は全く時間が取れず。
いよいよ定休日にひとりで作ってみるしかないと思っていたのですが、どうせ作るなら、教わりたい人や見てみたい人にも声をかけちゃおう!と思ったわけです。
明日10時から本店2階の厨房で作ります。希望される方は、本日中にお店にお電話くださいませ。
電話: 026-284-2934 小出まで
作るのは「梅」「パンダ」「黒豆」の3種です。
参加費用は材料費のみ。
所要時間は2時間ほどです。
「おやき」は信州のスローフードです。
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
2011年06月15日
柏餅
我が家で開催していた「小さな和み料理教室」。
わたしが昨年1年間大学院へ通っていたために、料理教室もお休みさせていただいておりました。
それがやっと今月から再開することができました。待っていてくださる人たちがいることに感謝です。
さて、今月は「柏餅」です。

「小豆餡」「味噌餡」「梅酢餡」の3種でしたが、断面を切って写真を撮っている時間がなくて残念。
一月遅れのお節句もすでに一週間も過ぎてからの「柏餅」でしたが、皆さん喜んでいただけました。
一緒に作ったのは「キノコのとろとろスープ」「糸寒天の中華風サラダ」ですが、写真またまたこんなもので

きょう定休日はまたまた蕎麦打ち修業なので、100歳のお師匠さんにもこれから柏餅を作って持っていくつもりです
「おやき」は信州のスローフードです。
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
わたしが昨年1年間大学院へ通っていたために、料理教室もお休みさせていただいておりました。
それがやっと今月から再開することができました。待っていてくださる人たちがいることに感謝です。
さて、今月は「柏餅」です。
「小豆餡」「味噌餡」「梅酢餡」の3種でしたが、断面を切って写真を撮っている時間がなくて残念。
一月遅れのお節句もすでに一週間も過ぎてからの「柏餅」でしたが、皆さん喜んでいただけました。
一緒に作ったのは「キノコのとろとろスープ」「糸寒天の中華風サラダ」ですが、写真またまたこんなもので

きょう定休日はまたまた蕎麦打ち修業なので、100歳のお師匠さんにもこれから柏餅を作って持っていくつもりです

「おやき」は信州のスローフードです。
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
2011年02月10日
花嫁修業??
花嫁修業?こんな歳になってそんなことあるわけない!

あははっ、イタリア料理教室、自分の勉強のために行ってまいりました。
作ったのは「ヤリイカのクスクス」
「サフラン入り生パスタのシーフードソース」
「松の実のタルト」
先生に「あなた、お粉の扱いが上手ねぇ」と言われ、思わずニンマリ

勉強のために行ったのに、美味しいものでお腹いっぱいになったら『やっぱり作るより食べる方がいいなあ』と至福の気分

そうじゃなくて、勉強、勉強


「おやき」は信州のスローフードです。
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
2010年02月09日
やしょうま
きのうは今年初めての我が家での料理教室でした。
毎年、年始めの教室はお題が決まっています。「やしょうま」です。
「やしょうま」も信州の郷土食として広がりを見せつつあって、元祖はやはり「おやき」と一緒で西山地域が盛んのようです。西山から大町、松本地域に伝わっているのは「絵やしょうま」とでもいうのでしょうか、金太郎飴のように顔や花、キャラクターなどカラフルなものが主流です。北信地域では昔から、ゴマや豆などを入れて、松や梅の形に仕上げるものが多いようです。
もともと「やしょうま」はお釈迦様の命日に仏壇に供える米の粉で作った細長い団子。やしょうまと言われるようになったのは諸説ありますが、団子の形が骨ばった馬の背中に似ているから「やせうま」からなまったとか、お釈迦様の臨終の時に、弟子の「やしょ」が団子を作ってあげたところ「やしょ、うまかったぞ」と言われ、やしょうまになったとも。
前置きが長くなりましたが、きのう教室で作ったのはこちら↓4種です。





「椿」「パンダ」「あじさい」「梅」
らしく見えないのもご愛嬌。このやしょうまは全て自然食材で色づけし、翌日まで柔らかいのが特徴です。見た目だけでなく、美味しさも絶品のやしょうま。レシピもお分けしますので、ご入用の方はメールにてご連絡くださいませ。
「おやき」は信州のスローフードです。
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/
毎年、年始めの教室はお題が決まっています。「やしょうま」です。
「やしょうま」も信州の郷土食として広がりを見せつつあって、元祖はやはり「おやき」と一緒で西山地域が盛んのようです。西山から大町、松本地域に伝わっているのは「絵やしょうま」とでもいうのでしょうか、金太郎飴のように顔や花、キャラクターなどカラフルなものが主流です。北信地域では昔から、ゴマや豆などを入れて、松や梅の形に仕上げるものが多いようです。
もともと「やしょうま」はお釈迦様の命日に仏壇に供える米の粉で作った細長い団子。やしょうまと言われるようになったのは諸説ありますが、団子の形が骨ばった馬の背中に似ているから「やせうま」からなまったとか、お釈迦様の臨終の時に、弟子の「やしょ」が団子を作ってあげたところ「やしょ、うまかったぞ」と言われ、やしょうまになったとも。
前置きが長くなりましたが、きのう教室で作ったのはこちら↓4種です。
「椿」「パンダ」「あじさい」「梅」
らしく見えないのもご愛嬌。このやしょうまは全て自然食材で色づけし、翌日まで柔らかいのが特徴です。見た目だけでなく、美味しさも絶品のやしょうま。レシピもお分けしますので、ご入用の方はメールにてご連絡くださいませ。
「おやき」は信州のスローフードです。
「ふきっ子のお八起」HP→http://www.fukikko-oyaki.com/